令和7年度施政方針
問い合わせ番号:17407-2183-0364
登録日:
令和7年度における町政運営の基本的な考え方
令和7年度は、町の主要施策であります「第2次香美町総合計画後期基本計画」及び重点施策であります「第2期香美町総合戦略」の最終年度を迎えます。計画の着実な実践を図り、町の将来像である『こどもたちに夢と未来をつなぐまち』の実現を目指すこととしております。
具体的には、「香美町の持続可能な町政運営を実現する予算」をコンセプトに、これまで取り組んできました施策の成果を再検証するとともに、住民サービスの向上に必要な事業の推進と財政の健全性維持の両立を進めてまいります。
また、以前からの課題でありました乳幼児・こども医療費の所得制限を撤廃し、子育て支援の充実を図るとともに、令和8年度を始期とする第3次香美町総合計画をはじめ各種計画を策定してまいります。
このような考えのもと、令和7年度の町政運営は、町民の皆様とともに、各種施策を推進してまいりたいと考えております。

2025年(令和7年)第152回香美町議会(定例会)
安全・安心なまちのしくみづくり(防災、生活環境、交通、地域活性化)
治山治水対策の推進
土砂災害の防止、がけ地の隣接地に居住する町民の生命と財産を守るため、県と急傾斜地崩壊対策事業に取り組むとともに、集中豪雨や台風等による被害を防ぐため、町管理河川の浚渫・改修工事等を実施します。
また、令和5年の台風7号で浸水被害があった油良・間室地内の治水対策について、事業主体である県と連携・協力しながら実施します。
消防防災力・防犯体制の強化
大規模災害時における救援、救護、復旧活動の拠点として山手地内に整備を進める地域防災拠点施設については、整備工事を継続して行い早期の完成を目指します。また、工事の進捗と合わせ、アクセス道路(舗装)や駐車場等の周辺整備を行います。
防災行政無線について、保守期限を迎える操作卓の更新やJアラート(全国瞬時警報システム)受信機の更新を行い、防災行政無線システムの安定運用を図ります。
また、防犯対策として、自治会等が行う防犯カメラ設置事業及びLED防犯灯整備事業について、引き続き助成制度による支援を行います。
消費生活トラブルの防止
様々な情報やサービスが複雑多様化し、またSNSを利用した契約に関するトラブルや悪質商法等の被害を訴える相談が後をたちません。
このことから、美方警察署、但馬消費生活センター等の関係機関と連携し、町民の皆様が安全で安心して暮らせるよう引き続き被害防止に向けた取組を推進します。
また、電話による高齢者に対する特殊詐欺事件が増加していることから、これらを未然に防止するため、令和7年度も継続して自動通話録音機能付き電話等の購入に対して補助を行います。
上下水道環境の整備
水道施設の計画的・効果的な整備と適切な維持管理を行い、清浄にして安全・安心な水の供給を図るため、水質対策、停電対策及び老朽施設の更新整備を行います。
下水道施設においても適切な維持管理を行い、快適な生活環境の保全と公共用水域の水質保全に努めるとともに、山手地区の新規加入申請に伴い、山手地区汚水管渠布設工事を行います。
また、効率的な施設管理を推進するため、香住浄化センター監視装置更新工事を行います。さらには、県が実施する国道482号改良工事に伴い、下水道施設の移設工事を行います。
道路網の整備
町民生活の利便性と安全性を確保するため、町内の橋梁の計画的な点検及び修繕工事や生活道路における改良及び災害防除工事、損傷の著しい路線の舗装修繕を実施します。また、将来の安定的な除雪体制を確保するための対策に取り組みます。
早期事業化が課題の山陰近畿自動車道の未事業化区間である佐津ICから(仮称)竹野IC間、主要地方道香住村岡線の加鹿野から三谷間(大乗寺BP2期)については、引き続き早期の事業着手、完成に向けて要望活動を行います。
さらに、現在事業中である国道9号笠波峠除雪拡幅事業についても、残る福岡地内の0.7kmの早期整備に向けて国の事業推進を支援します。
令和4年度に事業着手した小代区内の国道482号大谷バイパス2期工事につきましては、早期開通に向けて事業が進められています。
公共交通の維持
JR路線の維持に向け、沿線自治体と連携を図りJRとの協議を継続して進めます。また、鉄道利用促進助成を継続して実施するとともに、新たに近隣の沿線自治体と連携し、乗車券の購入額に応じたクーポンを発行する山陰本線ペイを実施し、利用促進を図ります。
町民バスの利便性向上のため、射添線のデマンド化の実証実験を行います。また、各公共交通の利用促進のため、引き続き助成制度による支援を行います。
地域の活動拠点の整備
令和7年度は香住自治区集会所、森区集会所の改築工事を進めるとともに、境自治会の集会所解体撤去に向けた設計を行います。
また、町民のコミュニティづくりの場として利用する区、自治会及び自治区の集会所の改修に補助を行い、地域コミュニティの活性化と交流の場の維持に努めます。
さらに、令和7年度から令和8年度にかけ、老朽化が著しい香美町地域活性センター「小代物産館」の解体撤去工事を進め、地域の皆様の交流拠点及び観光交流拠点となる新たな施設の整備を行います。
活力あるまちづくり(農林水産業の振興)
農業の振興・有害鳥獣対策
国内トップクラスの食用米を生産する町として、「香美町おいしいお米コンテスト」を開催し、生産者の栽培意欲と品質の向上を図っています。加えて、出荷先でもあるJAたじまのライスセンター再編に伴い、ライスセンターの乾燥調製施設改修経費を補助し、生産性の維持及び品質向上を図ります。
また、本町は県下一の「二十世紀梨」の産地であることから「香住なしの学校」の開設により、研修生を受け入れ新たな担い手の育成を図っています。さらに、インターンシップ宿泊支援補助金を設け、新たな研修生や後継者の育成を図ります。
さらに、農業生産基盤の確保のため中心的担い手や認定農業者の育成、農業法人の設立及び必要な農業用機械器具の導入に対する支援を引き続き行うとともに、新規就農者の育成・定着に向け、初期投資や経営安定を図るための費用に対し支援を行うとともに、令和7年度から新たな対策期間に入る第6期中山間地域等直接支払事業及び第3期多面的機能支払事業の取り組みを推進します。
有害鳥獣対策では、猟友会と協力して捕獲体制の強化を図ります。また、捕獲用具取得などの経費を支援し、有害鳥獣被害の軽減に努めます。
畜産の振興
「但馬牛の原産地」としての伝統を守り継承するため、優良系統の維持と繁殖雌牛の増頭を推進し生産規模の拡大による畜産農家の経営安定化を図ります。
また、世界農業遺産「人と牛が共生する美方地域の伝統的但馬牛飼育システム」を地域内外へ広くPRするため、シンポジウムの開催及び各種イベントでの啓発活動を図ります。
加えて、本システムを次世代へ継承するため保全事業を推進し、地域の関係者と連携を図りながら農畜産物の高付加価値化と地域活性化に取り組みます。
林業の振興
森林資源の適切な管理や有効活用のため、国県等と協力して各種事業を展開します。また、森林環境譲与税を活用した条件不利地間伐推進事業、環境保全型森林整備事業等に継続して取り組みます。
水産業の振興
「香美町の水産を考える会」による漁業・水産加工業全体のあり方の検討を引き続き行うとともに、「香美町魚食の普及の促進に関する条例」に基づき、魚食普及活動への支援を継続して行い、地域の水産物の消費拡大と地域経済の活性化を図ります。
活力あるまちづくり(観光、商工業の振興)
商工業の振興
地域の人材、資源、資金を活用した地域密着型の創業、新規事業に取り組む地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)に取り組む町内事業者を支援します。
人材確保のための特定技能制度や技能修得を目的とする技能実習生等の外国人を受け入れる事業者が年々増加していることから、外国人受入費用補助による事業者の負担軽減を図ります。また、従業員の社宅改修経費を支援し、従業員確保を図ります。
複数の仕事を組み合わせた新たな働き方(マルチワーク)による安定雇用を創出し、移住による地域づくり人材を確保する「香美町地域づくり事業協同組合」の活動を支援し、引き続き地域経済の維持と振興、地域の担い手育成に努めます。
観光業の振興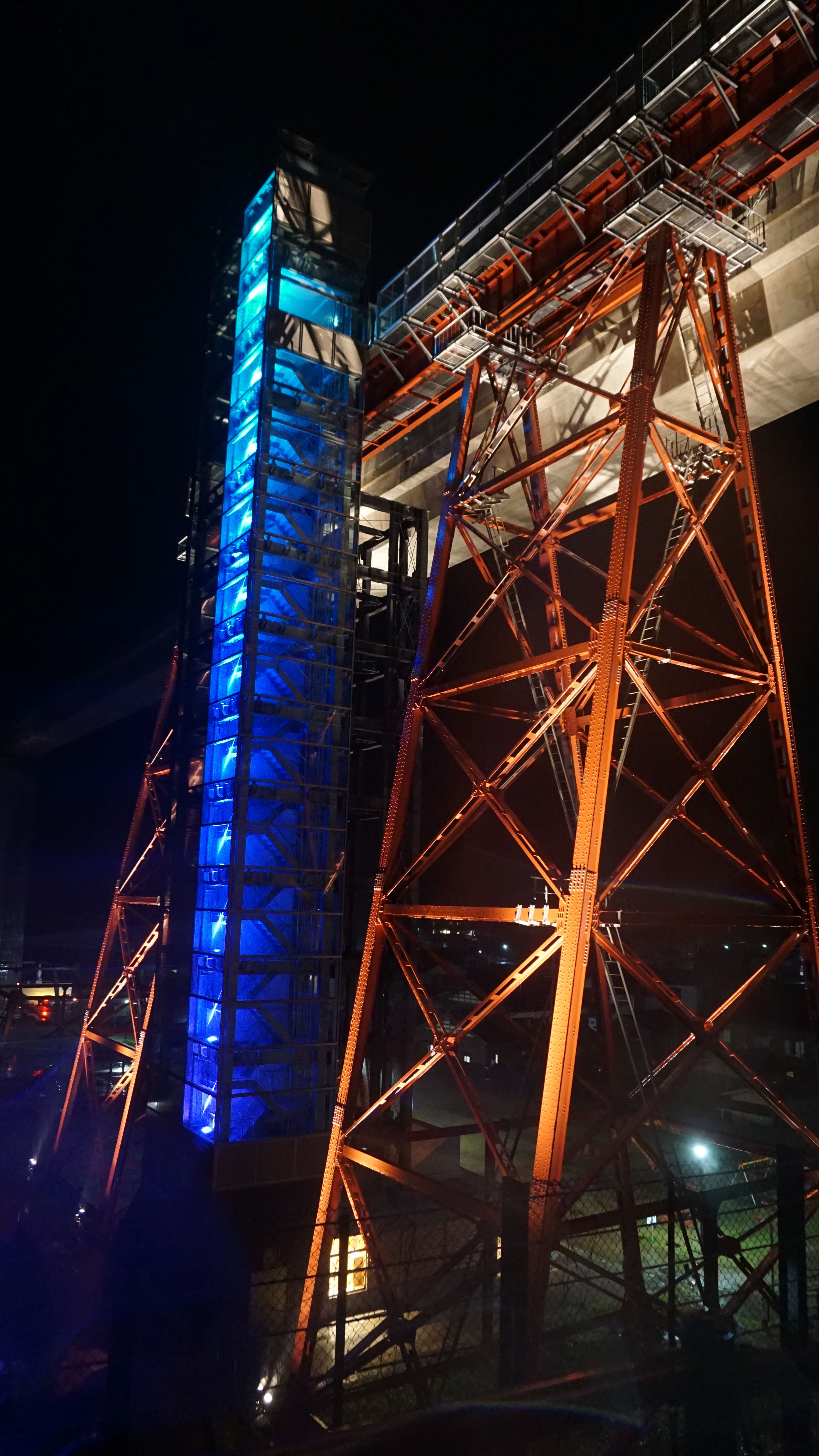
コロナ禍以降、観光需要はインバウンドを含め都市圏への偏在が見られ、依然として地方の状況はコロナ前の水準まで回復していません。
地域の観光資源を活かした魅力発信を行い、観光需要の増加に向け、観光イベントの支援を行うとともに、観光ホームページやSNSなどを通じた情報発信を行います。
麒麟のまち観光局を主体に本町を含む1市6町で構成する広域連携によるインバウンド受入環境整備や観光DX事業に取り組み、観光客の増加に努めます。
また、2025年日本国際博覧会(略称「大阪・関西万博」)においては、「ひょうごフィールドパビリオン」に認定された町内の取組を引き続き支援するとともに、但馬各市町と連携し、観光誘客を促進します。
山陰海岸ジオパークは令和6年度の世界審査で4年間の認定(グリーンカード)となりました。今後、一層のジオパーク活動の普及推進に取り組みます。
観光施設の整備
本町を訪れる多くの観光客に快適で安全に過ごしてもらうため、観光施設の整備を行います。令和7年度は、町内の道の駅4か所にEV急速充電器を整備するとともに、「ジオパークと海の文化館改修工事」、「道の駅村岡ファームガーデン舗装改修工事」等を行います。
御殿山公園を安全に利用いただくため、施設改修工事の設計業務に着手します。
将来を担うひとづくり(移住定住、結婚、子育て、教育)
移住定住対策
年々空き家が増加しています。利用可能な物件については空き家情報登録制度「空き家バンク」により移住・定住希望者への住まいとしての利用の提供を進めます。また、「まちなか移住相談室」を引き続き開設し、移住者相談に対応します。
さらに、町外からの移住希望者に対し本町の魅力や日常の生活情報を提供するため移住定住支援ウェブサイトのきめ細やかな更新を行います。併せてSNSを活用した情報発信を行うなど、町外からの移住促進に向けた取組を継続して推進します。
ふるさと納税の推進
ふるさと納税については、令和7年度で寄附額13億円突破を目指し、事業者との連携強化、魅力的な返礼品の開発や品目の拡充、PR体制の充実等を推進します。
また、寄附者の「香美町を応援したい」という思いを大切にし、町への寄附を継続的に行っていただくため、返礼品や同梱パンフレット等を通じた町の魅力発信を積極的に行っていきます。
これらシティプロモーションを通じた地域活性化を図り、町内事業者の売上向上、町の財源確保に繋げます。
結婚支援対策
町内高校生が人生設計について考えるライフデザインセミナーの開催、結婚等を前向きに考える機会として魅力アップセミナーを継続して実施するとともに、新たな婚活イベントを開催します。
また、地域内外の若者への交流の場の提供や因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏での結婚対策事業に引き続き取り組みます。
新たに結婚新生活支援事業に取り組み、新婚生活者の引っ越しや住居に係る費用の一部を支援します。
妊娠・出産・子育て支援の充実
令和5年2月より実施してきた「出産・子育て応援交付金事業」に代わり、令和7年度より妊娠期から出産、子育て期まで一貫して身近な相談と必要な支援につなぐ「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と経済的支援を目的とした「妊婦のための支援給付事業」を新たに実施します。
また、町独自施策として実施している「かみっこオムツ券交付事業」を活用して切れ目のない子育て支援を推進し、本町で子育てをしたいという思いを抱くことのできる仕組みを整えます。
妊産婦の健康診査費用や新生児聴覚検査費用の全額助成に加え、乳児の1か月児健康診査費用の全額助成を新たに実施し、さらなる子育て支援の充実を進めます。
乳幼児及びこども医療費の完全無料化
乳幼児及び子どもに係る医療費助成について、令和7年度より所得制限を撤廃し、医療費の完全無料化を実施し、すべての保護者の負担軽減を図ります。
子育て・子育ち環境の充実
保護者が疾病等の要因により、一時的に家庭での児童の養育が困難となった場合に、児童福祉施設において一定期間、養育する現行の制度に、新たに「里親」家庭を加えることで、子育て家庭の支援を強化します。
その他、児童福祉法に基づき、療養の必要な18歳未満の子どもに提供される児童相談支援・児童発達支援サービスに係る経費を障害児通園施設に支援することで、子育て環境の向上を図ります。
教育振興基本計画の推進
令和8年度に予定している香美町教育振興基本計画の見直しに向け、児童生徒、保護者、教職員及び町民を対象としたアンケート調査を実施し、現計画の検証を行います。
ICT環境の整備
GIGAスクール構想で整備したタブレット端末が5年を経過するにあたり、機器の故障等により子どもたちの学びを止めることがないよう計画的に更新を行います。
学校再編
令和4年度に策定しました学校再編計画に基づき、村岡区小学校等再編検討委員会を設置し、就学前施設を含めた村岡区の学校園の再編の検討を行います。また、引き続き香住区就学前施設の再編に向けた検討、香住区小学校2次再編に向けた準備を進めます。
部活動地域移行(地域展開)の推進
全国的に進められています中学校部活動の地域移行(地域展開)について、令和8年度に実現可能な部活動から段階的に地域移行(地域展開)が実施できるよう、町部活動指導員の人材バンクの設置及び登録の推進、複数校合同による部活動実施の機会の設定などの取組を進めます。
教育環境の整備
老朽化した村岡小学校プールの改修を行います。また、村岡中学校体育館の空調整備を行い、教育環境の向上と災害時の避難所としての機能強化を図ります。さらに、香住第一中学校体育館への空調整備に向けた設計を行います。
大学連携の推進
兵庫県立芸術文化観光専門職大学に併設する地域リサーチ&イノベーションセンターと連携を図り、地域課題の解決や地域活性化につながる取組を引き続き行います。また、高校コミュニケーション教育を継続して実施します。
スポーツの振興
多くの町民が各種スポーツに親しみ、楽しまれる中、スポーツ指導者の資格取得などに必要となります研修費を補助し、指導者の資質向上を推進します。
競技では、一流アスリートの招聘や日本体育大学との連携協定によるスポーツ講習会の開催、香美町スポーツ協会20周年記念事業のスポーツ講演会により、国内外で活躍するスポーツ選手の育成を目指すとともに、町民へのスポーツの推進、健康づくりに取り組みます。
また、施設整備として、香住B&G海洋センター体育館の天井等の修繕を行い、スポーツを行う施設の環境向上を図るほか、令和9年度に開催決定となりましたワールドマスターズゲームズ2027関西の大会成功に向け、普及啓発や受入体制の整備を図ります。
図書事業の充実
3つの町民運動である「読書」を推進するため、村岡区、小代区と同様、引き続き香住区においても移動図書館車の試験運行を行い、利便性の向上に努めます。
また、読書時間が子どもの学力向上に相関するという調査結果から、幼少期からの読書の習慣づけや、文章を読む力を身につけるため、学校図書室の整理や推奨本リストの掲示を行うとともに、公民館図書室の蔵書を充実します。
芸術文化の振興
香美町文化芸術振興計画に基づき、地域の人々が多様な文化芸術に触れ、創造性・感受性を育み、心豊かな生活が送れるよう事業を引き続き進めます。
芸術面では、より多くの町民が芸術に触れる機会を創出するため、豊岡演劇祭2025香美町公演、クラシックコンサートの開催や、バイオリン等楽器の演奏講座の開設を行います。文化面では、大乗寺障壁画収蔵庫の改修、三番叟衣装の整備への支援を行い、文化、文化財の保護保全に努めます。
安心な暮らしづくり(保健、医療、福祉)
健康づくりの推進
町民が自分らしく健やかに暮らせる「健康長寿」の実現を目指し、令和5年度に策定しました第3次香美町健康増進計画及び第3次香美町食育推進計画に基づき、健康づくり事業を進めます。
また、季節性インフルエンザ予防接種をはじめ、令和6年度から実施している高齢者新型コロナワクチン接種及び令和7年度より新たに定期接種に位置付けられた高齢者帯状疱疹予防接種など各種予防接種に係る費用の一部助成による負担軽減の継続と特定健康診査及びがん検診などの受診促進を図り、健康で安心して暮らせるまちづくりを推進します。
公立香住病院の運営
令和7年度は、常勤医師1名が定年のため非常勤となりますが、県からの派遣医師が1名増の3名となり、常勤医師は現状7名を維持します。非常勤医師は1名増の4名で合計11名の医師体制となります。今後においてもより充実した診療体制に努めます。
また、令和7年1月に総合診療科診察室の拡張を行い、今後も引き続き医療環境の整備を行っていきます。
町民の皆様に信頼され、安全で安心できる質の高い医療を提供していくため、引き続き医師及び医療技術者の確保に全力で取り組むとともに、病院経営の効率化に努め、将来にわたり持続可能な病院経営を目指します。
高齢者福祉の充実
第9期の「香美町高齢者福祉計画」及び「香美町介護保険事業計画」に基づき、「みんなで支えあい自分らしく安心して暮らせるまちづくり」を目指し、「地域包括ケアシステムの拡充」、「介護予防の推進」、「認知症施策の推進」、「在宅医療・介護連携の推進」に引き続き取り組みます。
また、認知症高齢者の行方不明事案が年間に数件発生しており、幸いにも重大な結果には至っておりませんが、行方不明となった場合に早期に発見できるよう「GPS端末」の利用者費用の一部を助成します。
さらに、医療従事者・介護従事者の業務の効率化による負担軽減及び介護サービス利用者の利便性の向上のため町内の内科の医療機関、介護サービス事業者間の情報連携ツールとしてICT技術を活用する事業者に対して助成を行います。
障害者福祉の充実
第4期香美町障害者福祉計画に基づき、「みんな元気で共に支え合うまちづくり」を目指し、障害者福祉サービスや相談支援体制の充実など、自立支援や社会参加への環境づくりとともに、障害のある子どもへの療育について引き続き取り組みます。
また、障害者支援施設の老朽化対策及びサービスの質の確保を目的として、課題となっている香住心身障害者(児)共同生活ホーム等の改修について検討します。
住民サービスの向上(行財政運営)
マイナンバーカードの取得促進
マイナンバーカードの取得については、通常の受付以外に時間外窓口の開設や休日受付を行うなどの利便性を図ることにより、多くの方に申請をいただきました。
今後、デジタル化によるマイナンバーカードの需要の増加も見込まれるとともに、令和7年度はマイナンバーカードの取得時期が早い方が更新時期を迎えることから、町民の皆様が円滑な取得や更新手続が行えるよう取り組みます。
デジタル化の推進
国が進める「情報システムの標準化・共通化」移行期限である令和7年度を迎え、早期の移行完了を目指し、取組を進めます。
また、DX推進による利便性の向上を図るため、令和7年度からは、従来の書面による申請手続きに加え、インターネットを利用したオンライン申請を開始します。
情報環境の整備と情報発信の充実
光回線サービス未提供の16集落をはじめとする町内の未提供世帯に対し、光回線サービスに代わるインターネット接続方法として衛星通信サービスへの加入に際し、初期費用の一部を補助します。
また、現在のホームページは保守期限を迎えることから、ホームページのリニューアルを行います。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0796-36-1962
FAX番号:0796-36-3809

