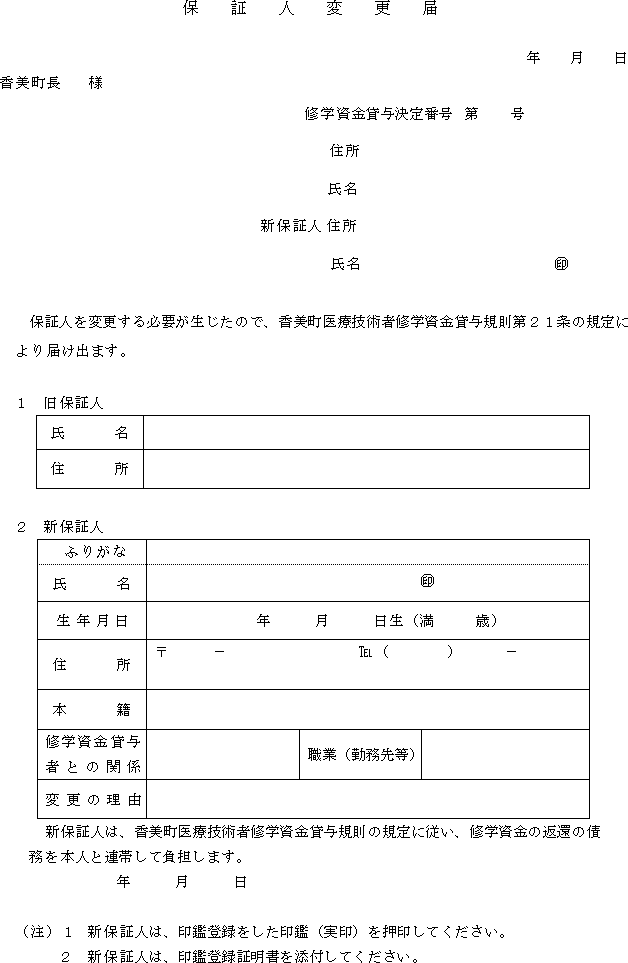○香美町医療技術者修学資金貸与規則
平成29年3月31日規則第17号
香美町医療技術者修学資金貸与規則
(目的)
第1条 この規則は、香美町の医療の充実のため、必要な医療技術者の養成及び確保に資することを目的に、医療技術者を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、将来、公立香住病院(以下「病院」という。)において医療技術者の業務(以下「業務」という。)に従事しようとする者に対し、医療技術者修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療技術者 看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士及び薬剤師
(2) 養成施設
ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号から第3号までに規定する学校又は看護師養成所
イ 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1項に規定する学校又は診療放射技師線養成所
ウ 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号に規定する学校又は臨床検査技師養成所
エ 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号及び第2号に規定する学校若しくは理学療法士養成所又は作業療法士養成所
オ 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号に規定する学校又は臨床工学技士養成所
カ 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第15条第1号に規定する学校
キ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の医療技術者を養成する課題を有する学部又は学科
(3) 修学資金 前号に掲げる養成施設の修学に要する費用
(修学資金の貸与)
第3条 町長は、養成施設に在学している者で、卒業後に病院に勤務しようとする者に対し、毎年度予算の範囲内において修学資金を貸与することができる。
(貸与の額)
第4条 前条の修学資金として貸与する金額は、月額60,000円を上限とする。
2 修学資金は無利息で貸与するものとする。
(貸与の方法)
第5条 修学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、貸与の決定をした日の属する月)から養成施設を卒業し、又は修了する日の属する月までとし、毎月貸与するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸与の申請)
第6条 第3条の規定により修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、香美町医療技術者修学資金貸与申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 履歴書(市販のもの)
(2) 健康診断書(申請の日前2か月以内に公的医療機関で作成されたもの)
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 在学証明書
(5) 保証書(様式第3号)
(6) 本人及び本人が属する世帯全員の住民票の写し(本籍地表示入り)
2 町長は、前項に規定する書類のほか、修学資金の貸与のため必要と認める書類の提出を求めることができる。
(保証人)
第7条 申請者は、独立した生計を営む成年者2人の保証人を立てなければならない。保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して当該貸与に係る債務を負担するものとする。
2 申請者が未成年者である場合は、保証人のうち1人は、その法定代理人とする。
3 保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな保証人を立てなければならない。
(貸与の決定)
第8条 町長は、毎年度予算の範囲内において、第6条の申請に基づき提出された書類の審査及び面接により修学資金の貸与の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項により修学資金の貸与の可否を決定し、貸与することを決定したときは香美町医療技術者修学資金貸与決定通知書(様式第4号)により、貸与しないことに決定したときは香美町医療技術者修学資金貸与決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付の申請)
第9条 申請者は、前条に規定する修学資金の貸与決定通知書を受けたときは、速やかに香美町医療技術者修学資金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(貸与の取り消し)
第10条 町長は、修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与を取り消すことができる。
(1) 養成施設に在学しなくなったとき。
(2) 被貸与者の学業成績が著しく不良となったと町長が認めるとき。
(3) 被貸与者が心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと町長が認めるとき。
(4) 被貸与者が修学資金の貸与を辞退したとき。
(5) 被貸与者が死亡し、又は所在不明になったとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、修学資金を貸与することが不適当と町長が認めるとき。
2 前項の規定による修学資金の貸与の取り消しは、当該事由に該当することとなった日の属する月の翌月分からの貸与を取り消すものとする。ただし、当該月以降の分として既に貸与した修学資金があるときは、貸与期間の翌月分以後の分として貸与したものとみなす。
3 町長は、修学資金の貸与の取り消しを決定したときは、被貸与者に対し香美町医療技術者修学資金貸与取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
4 被貸与者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、香美町医療技術者修学資金貸与辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(貸与の停止)
第11条 町長は、被貸与者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該事由が生じた日の属する月の属する月の翌月から復学した日の属する月まで、修学資金の貸与を停止することができる。
2 町長は、前項に掲げる修学資金の貸与の停止を決定したときは、当該被貸与者に対し香美町医療技術者修学資金貸与停止通知書(様式第9号)により通知するものとする。
3 第1項の規定により貸与の停止を行った場合において、既に貸与された修学資金があるときは、当該被貸与者が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与したものとみなす。
4 町長は、第1項に規定する場合を除くほか、被貸与者の学業成績の不良その他修学資金の貸与を行うことが適当でないと認めるときは、必要な期間修学資金の貸与を停止することができる。
(貸与の再開の手続き)
第12条 前条の規定により修学資金の貸与が停止となった被貸与者が、復学して再び修学資金の貸与を受けようとするときは、香美町医療技術者修学資金貸与再開申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、修学資金の貸与の再開を決定したときは、香美町医療技術者修学資金貸与再開決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(借用証書の提出)
第13条 被貸与者及び連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、すでに貸与を受けた修学資金の全額について、直ちに香美町医療技術者修学資金借用証書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 貸与期間が終了したとき。
(2) 第10条第1項の規定により貸与が取り消しとなったとき。
(3) 第11条第1項の規定により貸与が停止となったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(返還)
第14条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与期間に相当する期間内に、月賦又は半年賦の均等払いの方法により、貸与を受けた修学資金に相当する額を返還しなければならない。ただし、全部又は一部を繰り上げて返還することを妨げない。
(1) 第10条第1項の規定により修学資金の貸与を取り消されたとき。
(2) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに、免許を取得しなかったとき。
(3) 免許の取得後、直ちに(看護師については2年以内に)病院において業務に従事しなかったとき。
(4) 病院において業務に従事した期間(以下「業務従事期間」という。)が、第16条第1号の期間に満たなかったとき。
(5) 業務従事期間中に業務以外の理由により死亡し、又は病院の業務に従事できなくなったとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。
(返還の債務の履行の猶予)
第15条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間について、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(1) 医療技術者の免許を取得しようとするとき。ただし、その期間は、養成施設卒業後1年を限度とする。
(2) 次条第1号に規定する返還債務の免除要件に該当する期間において、病院において医療技術者として勤務しているとき。
(3) 養成施設の卒業後、更に他の養成施設に在学し、卒業後病院において業務に従事できる見込みがあると認める場合は、必要と認める期間
(4) 災害、病気その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると町長が認める場合は、必要と認める期間
2 前項の規定による返還の猶予を受けようとする者は、同条各号に掲げる事由が生じた日から起算して1か月以内に、香美町医療技術者修学資金返還猶予申請書(様式第13号)に前項各号に掲げる事由を証明する書類を添付して町長に提出し、その承認を得なければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、返還の猶予を承認したときは香美町医療技術者修学資金返還猶予承認通知書(様式第14号)により、返還の猶予を承認しないときは香美町医療技術者修学資金返還猶予不承認通知書(様式第15号)により返還の猶予を受けようとする者に通知するものとする。
(返還の債務の当然免除)
第16条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務の全部を免除することができる。
(1) 養成施設を卒業した日から起算して1年以内に医療技術者の免許(以下「免許」という。)を取得し、かつ直ちに(看護師については2年以内に)病院において医療技術者として業務に従事し、連続する業務従事期間が貸与期間に相当する期間(以下「業務に従事すべき期間」という。)に達したとき。
(2) 被貸与者が業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 前項第1号の場合において、病院に勤務した後、病気その他町長がやむをえないと認める理由により勤務できなくなり、その理由がなくなった後、直ちに勤務した者の業務従事期間については、業務を継続することができなくなった日(以下「業務中断日」という。)までに勤務した期間に、業務中断日の後に勤務した期間を乗じた期間を業務従事期間とする。
(返還の債務の裁量免除)
第17条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなったと認めるときは、返還の履行期限が到来していない部分にかかる修学資金の返還の全部又は一部を免除することができる。
(1) 被貸与者が死亡したとき、又は心身若しくは身体に著しい故障が生じたことにより修学資金を返還することができなくなったと認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、修学資金の債務の一部を免除する必要があると認めたとき。
(返還の債務の免除の申請)
第18条 第16条及び第17条の規定による返還の債務の免除を受けようとする被貸与者(被貸与者が死亡したときは保証人)は、免除の事由に該当することとなった日から起算して1か月以内に、香美町医療技術者修学資金返還免除申請書(様式第16号)に、当該事由に該当する旨を証する書面を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、承認することを決定したときは香美町医療技術者修学資金返還免除承認通知書(様式第17号)により、承認しないことを決定したときは香美町医療技術者修学資金返還免除不承認通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(返還の債務を免除する額)
第19条 第16条第1号の規定による修学資金返還の債務の免除は、第15条第2号の規定により修学資金の返還を猶予されている期間において、毎年12月に次項で定める金額の修学資金の返還を免除するものとする。ただし、最終年度は第16条第1号で定める期間を満了した月とする。
2 前項で免除する返還の債務の金額は、貸与した修学資金の総額にその年の業務従事期間の月数を乗じ、これを第16条第1号で定める業務に従事すべき期間の月数で除して得た金額とする。
3 第1項の規定により、返還の債務を免除する金額に百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとし、最終年度の免除額で調整するものとする。
4 被貸与者が業務に従事すべき期間に満たないで病院の医療技術者でなくなる場合は、貸与した修学資金の総額に病院の医療技術者でなくなる日の属する月の前月までの業務従事期間の月数を乗じ、業務に従事すべき月数で除した金額をその年の債務免除の金額とする。ただし、この金額に百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
5 前項の場合において、病院の医療技術者でなくなる日までに免除された修学資金の額と貸与された修学資金の額との差額は、第14条第1項の規定により返還しなければならない。
(届出義務)
第20条 被貸与者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を町長にそれぞれ届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。 住所・氏名変更届(様式第19号)
(2) 退学、休学若しくは停学の処分を受けたとき、復学したとき又は心身の故障のため養成施設を卒業する見込みがなくなったとき。 医療技術者養成課程履修状況変更届(様式第20号)
(3) 医療技術者の免許を取得したとき。 医療技術者免許取得届(様式第21号)
(4) 第15条第1項第2号の規定に該当し、返還債務の猶予を受けている期間に、病院の医療技術者としてその業務に従事しなくなったとき。 勤務辞退届(様式第22号)
2 保証人は、被貸与者が死亡したときは、死亡届(様式第23号)に死亡診断書又は除籍抄本を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(保証人の異動及び変更)
第21条 被貸与者は、保証人の氏名又は住所に変更があったとき、保証人が死亡したとき若しくは保証人に破産手続開始の決定その他の保証人として適当でない事由が生じたときは、速やかに新たな保証人を立て、保証人の身分異動届(様式第24号)及び保証人変更届(様式第25号)により町長に届け出なければならない。
2 被貸与者は、前項に規定する場合のほか、保証人を変更しようとするときは、保証人変更届により町長に届け出なければならない。
(延滞利息)
第22条 被貸与者若しくは連帯保証人は、正当な理由がなく、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項で定める延滞利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(貸与の特例)
第23条 町長は、本町以外の修学資金制度による資金(以下「他の修学資金」という。)の貸与を受け、養成施設に在学する者で、養成施設を卒業後に医療技術者として病院に勤務しようとする者又はこれに準ずる者が、他の修学資金の返還の債務を有するときは、これに相当する金額を修学資金として貸与することができる。ただし、第4条第1項に規定する額を上限とする。
2 第5条から前条(第10条第2項及び第11条第3項を除く。)までの規定は、前項の規定により修学資金を貸与する場合について準用する。この場合において、第16条中「連続する業務従事期間が貸与期間に相当する期間(以下「業務に従事すべき期間」という。)に達したとき。」とあるのは、「町長が認める期間」とする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
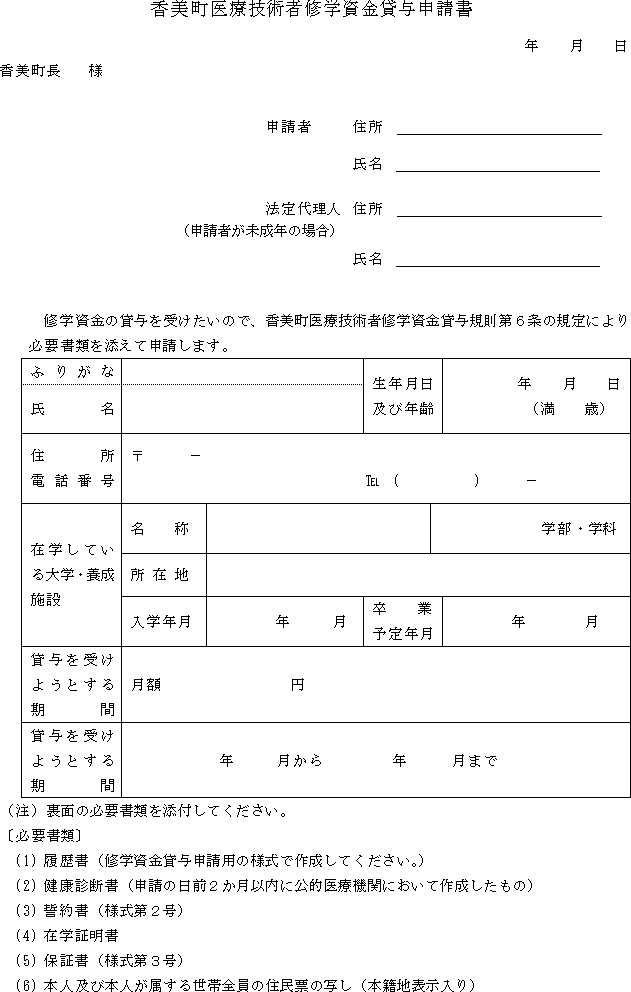
様式第2号(第6条関係)
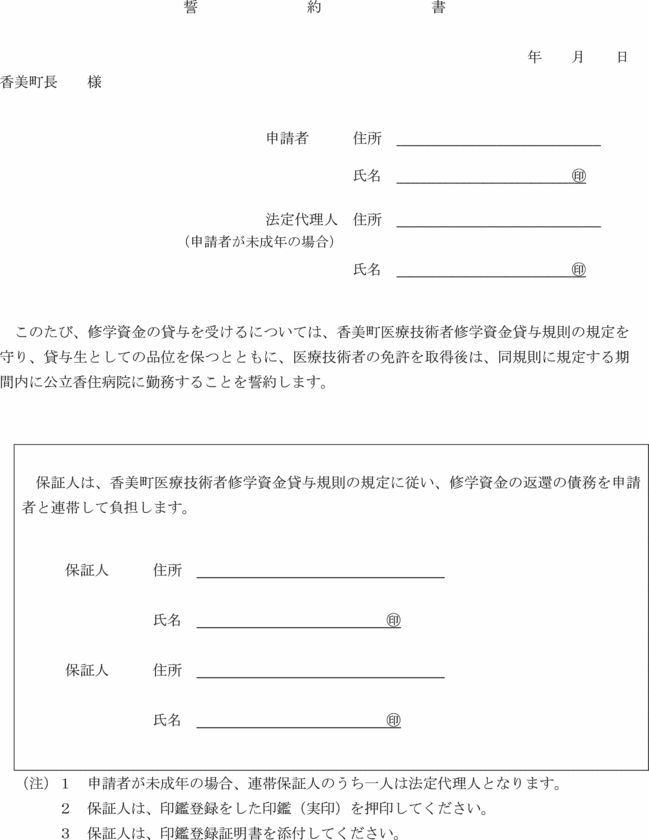
様式第3号(第6条関係)
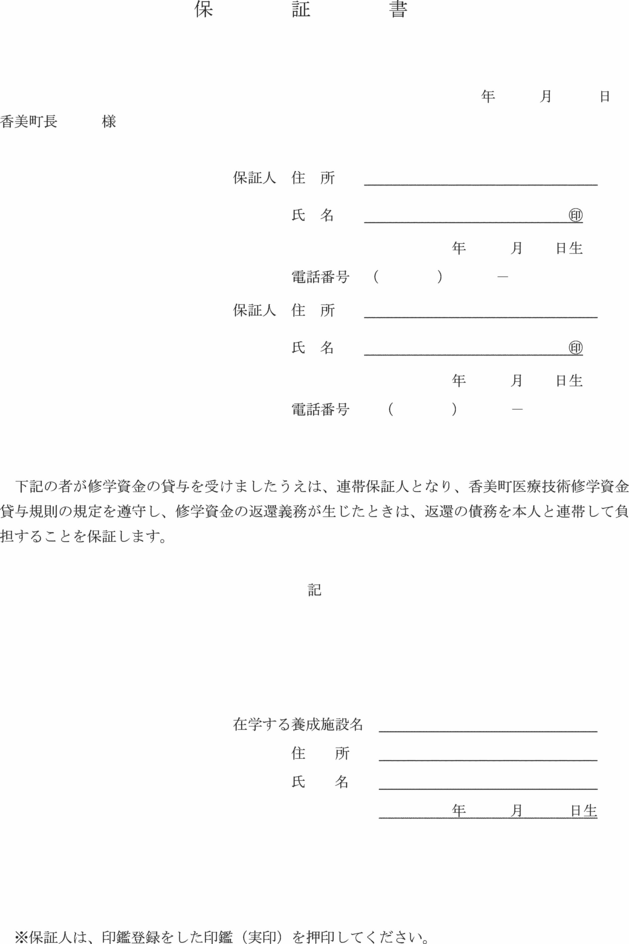
様式第4号(第8条関係)
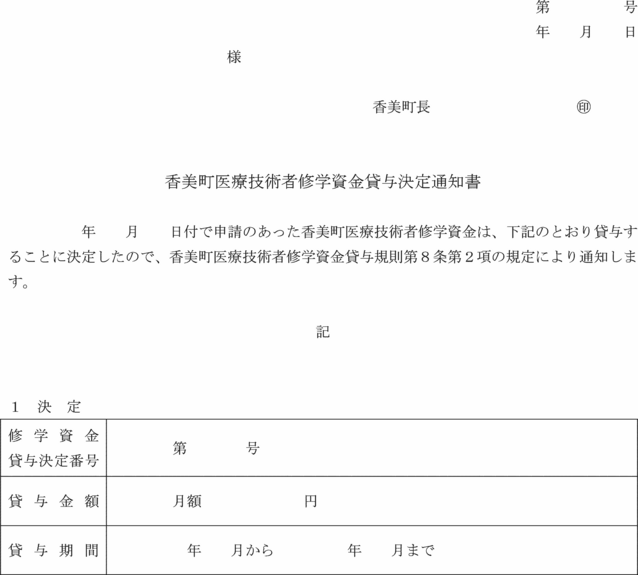
様式第5号(第8条関係)
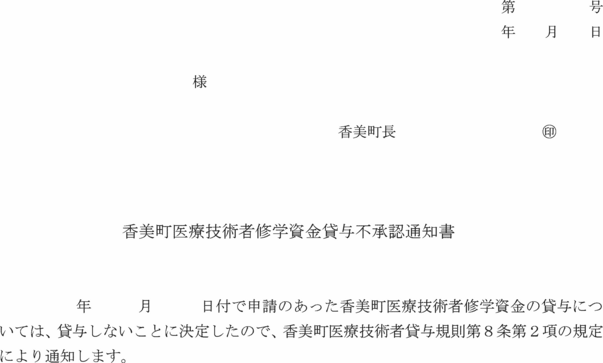
様式第6号(第9条関係)
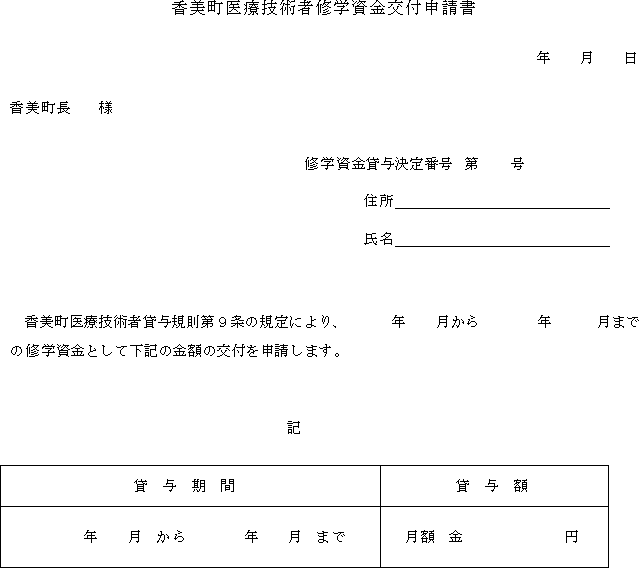
様式第7号(第10条関係)
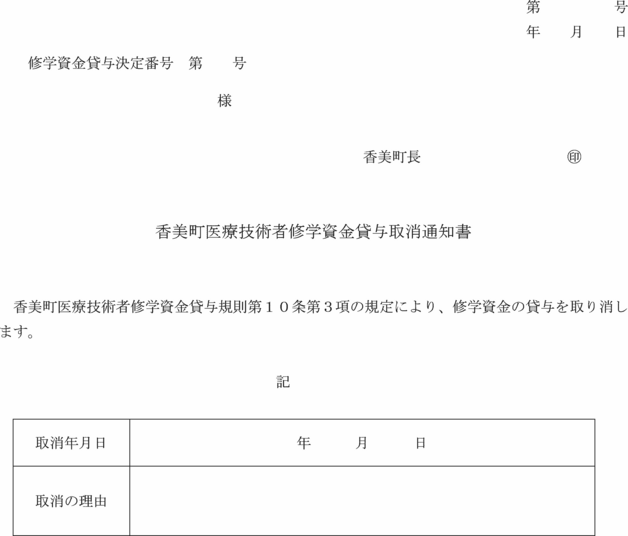
様式第8号(第10条関係)
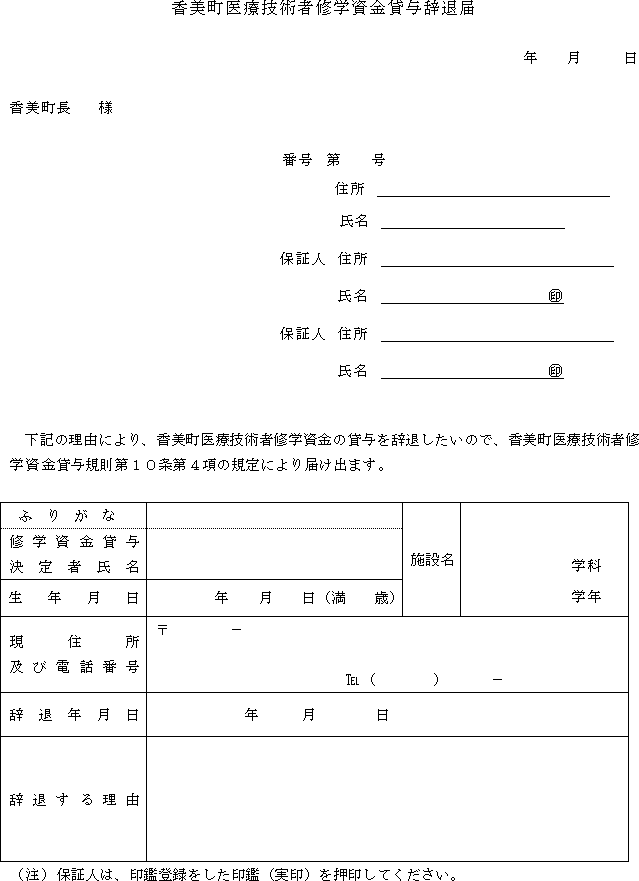
様式第9号(第11条関係)
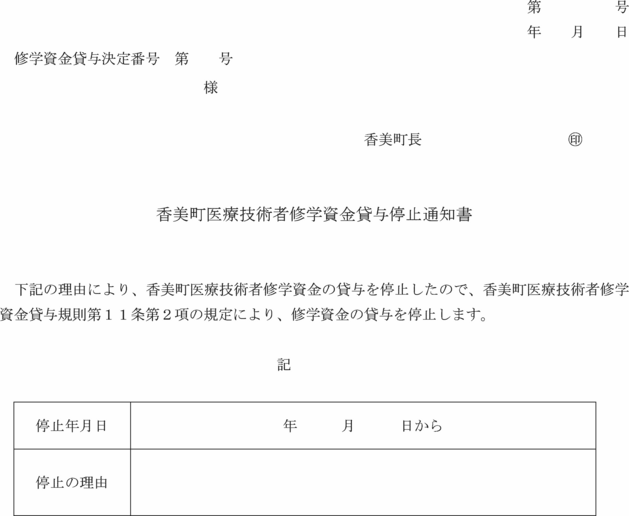
様式第10号(第12条関係)
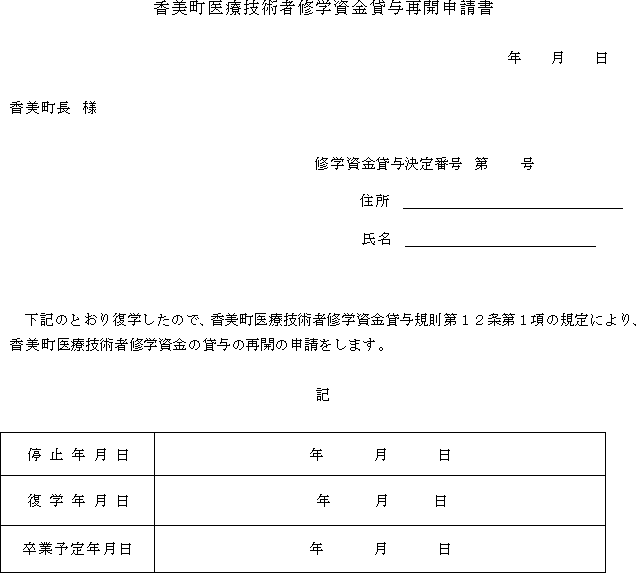
様式第11号(第12条関係)
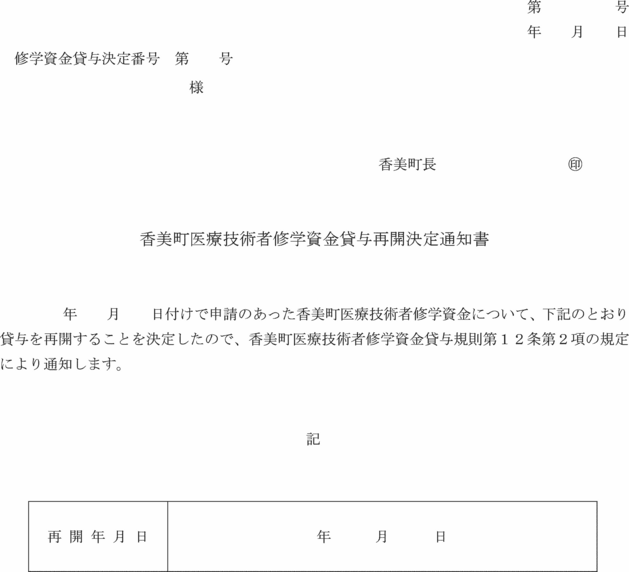
様式第12号(第13条関係)
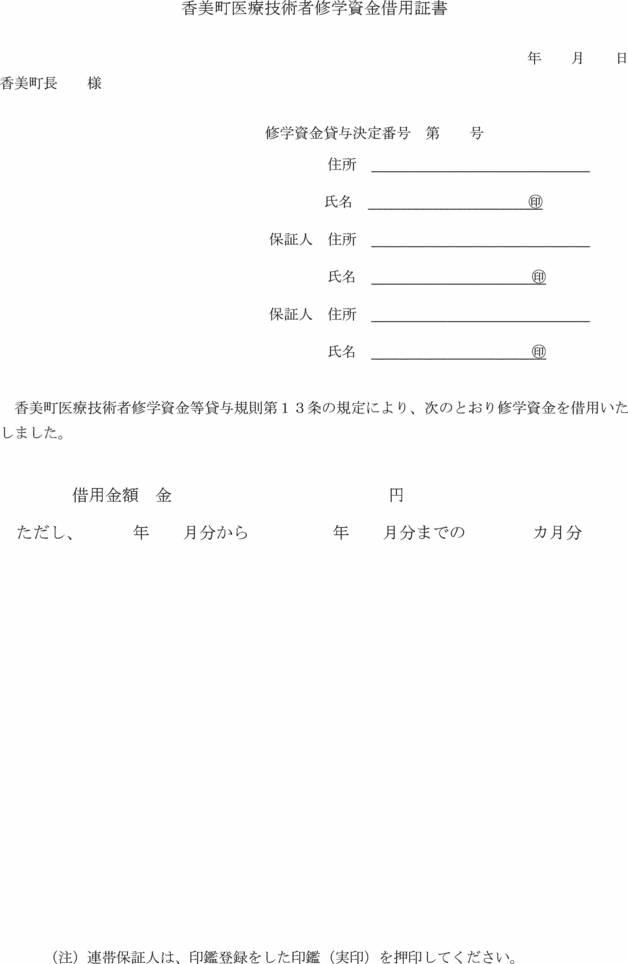
様式第13号(第15条関係)
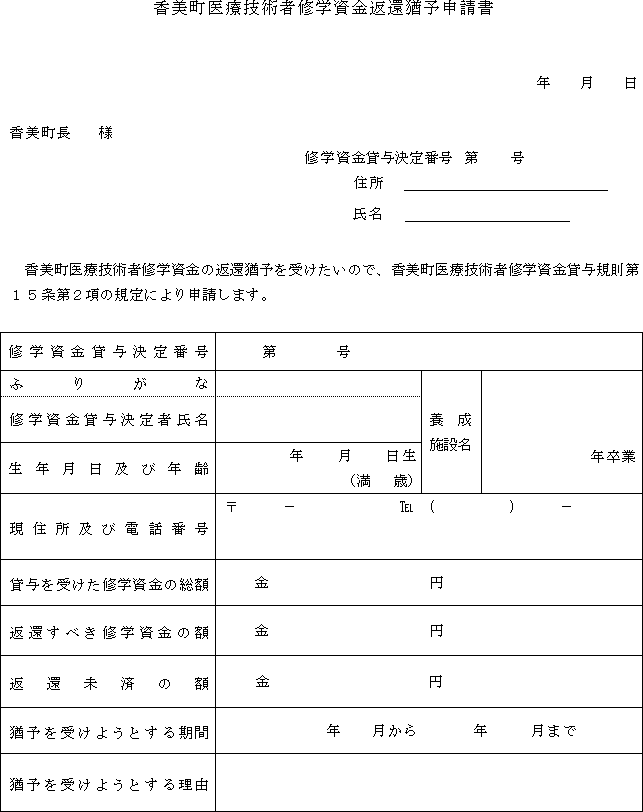
様式第14号(第15条関係)
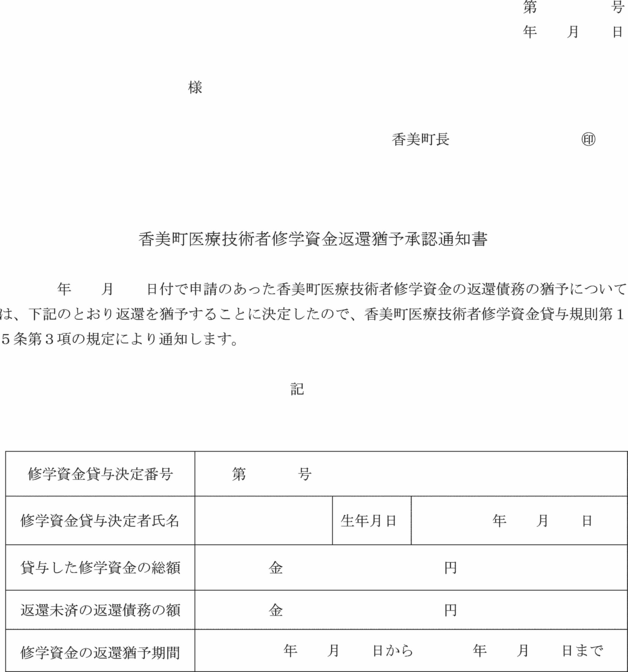
様式第15号(第15条関係)
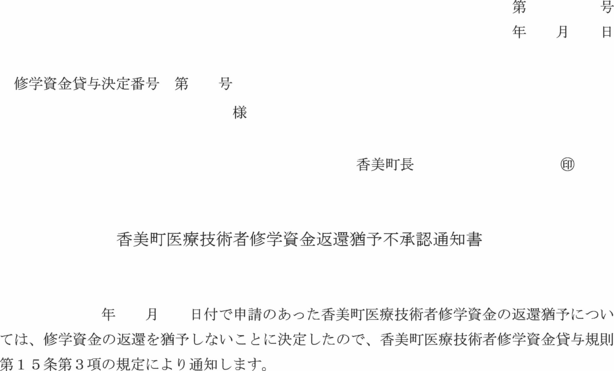
様式第16号(第18条関係)
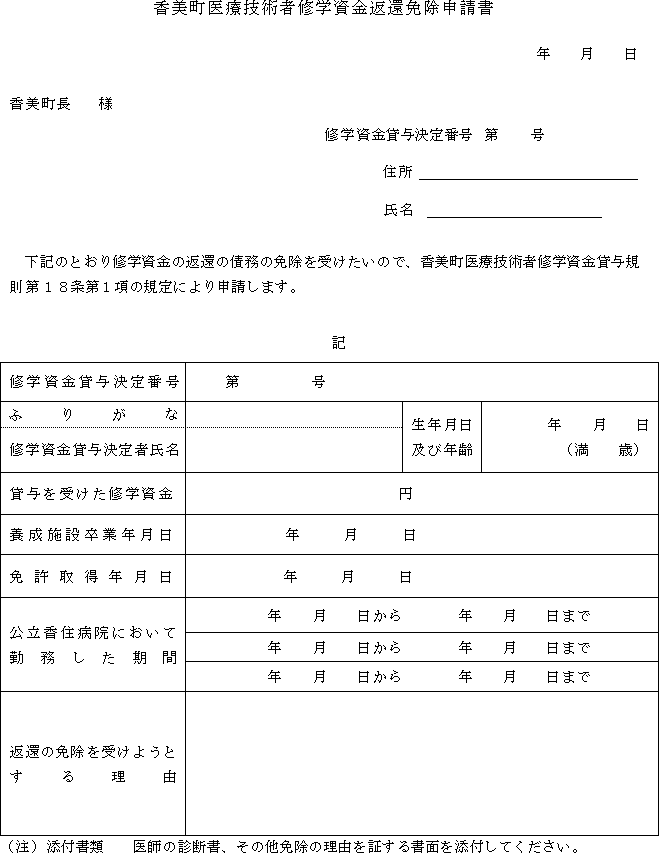
様式第17号(第18条関係)
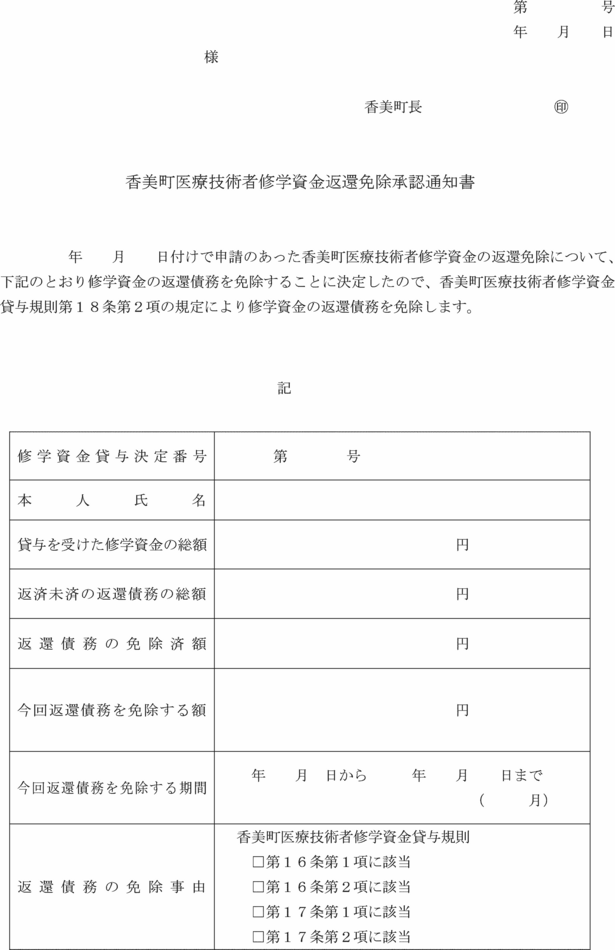
様式第18号(第18条関係)
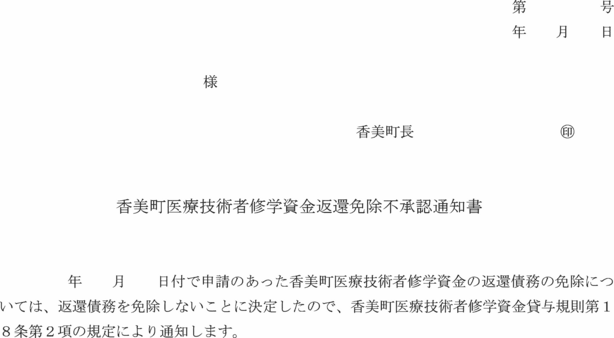
様式第19号(第20条関係)
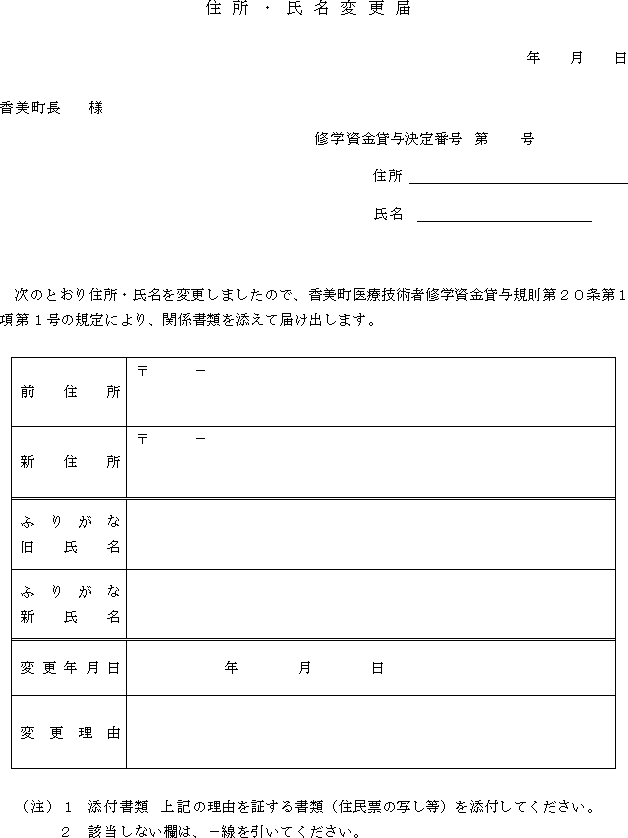
様式第20号(第20条関係)
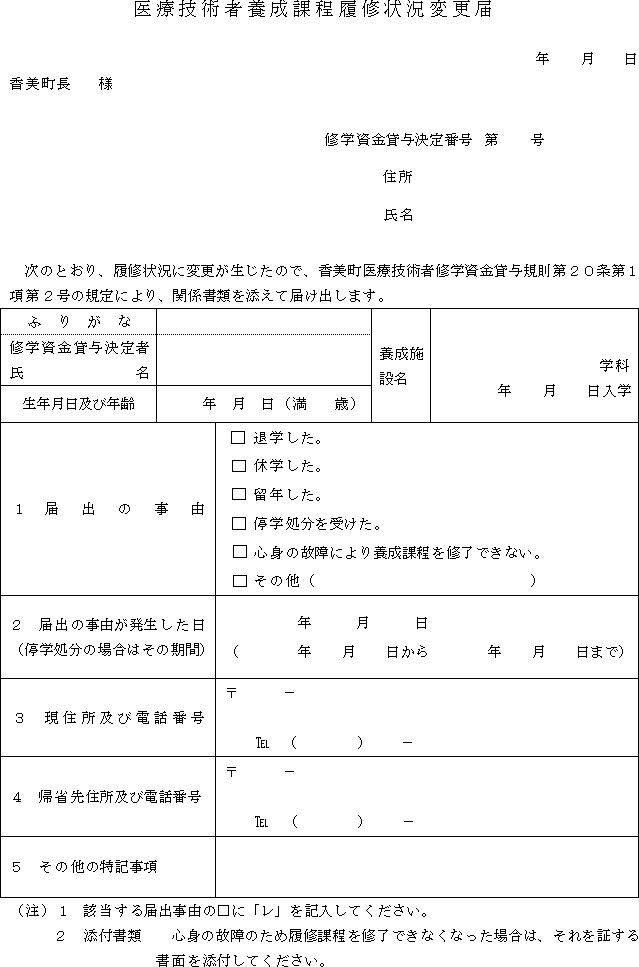
様式第21号(第20条関係)
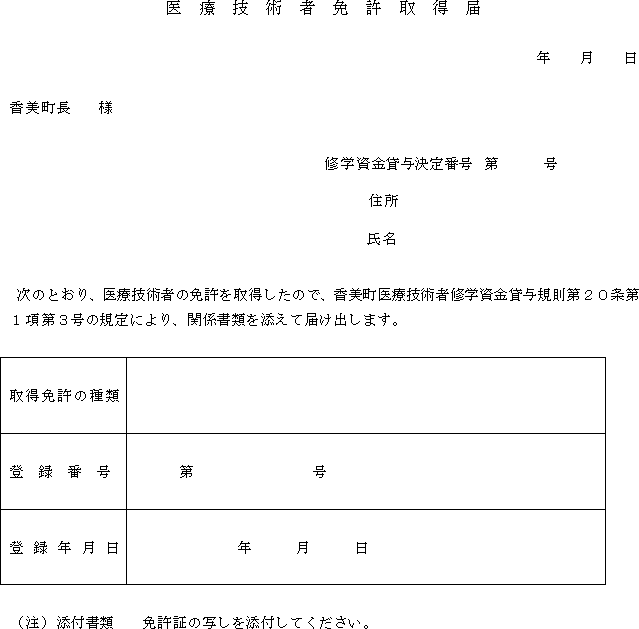
様式第22号(第20条関係)
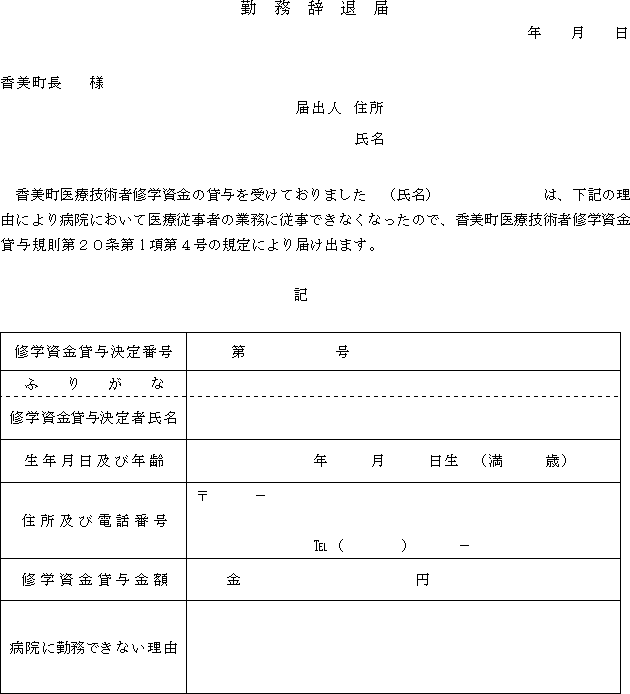
様式第23号(第20条関係)
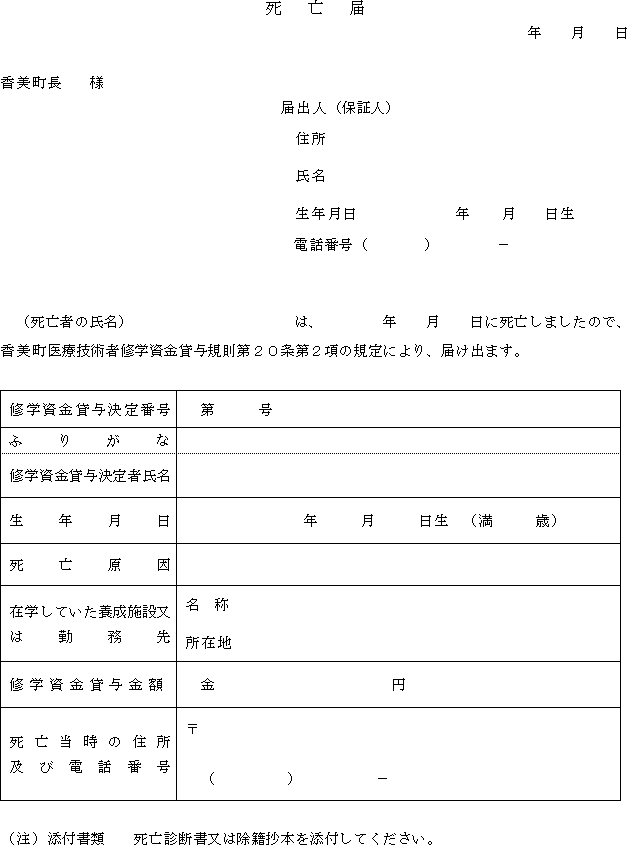
様式第24号(第21条関係)
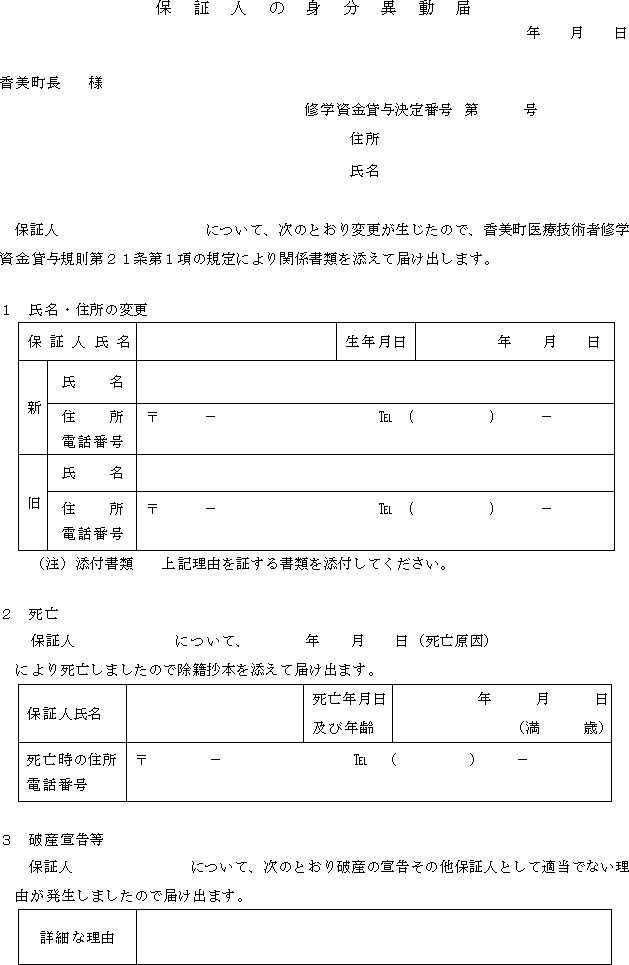
様式第25号(第21条関係)