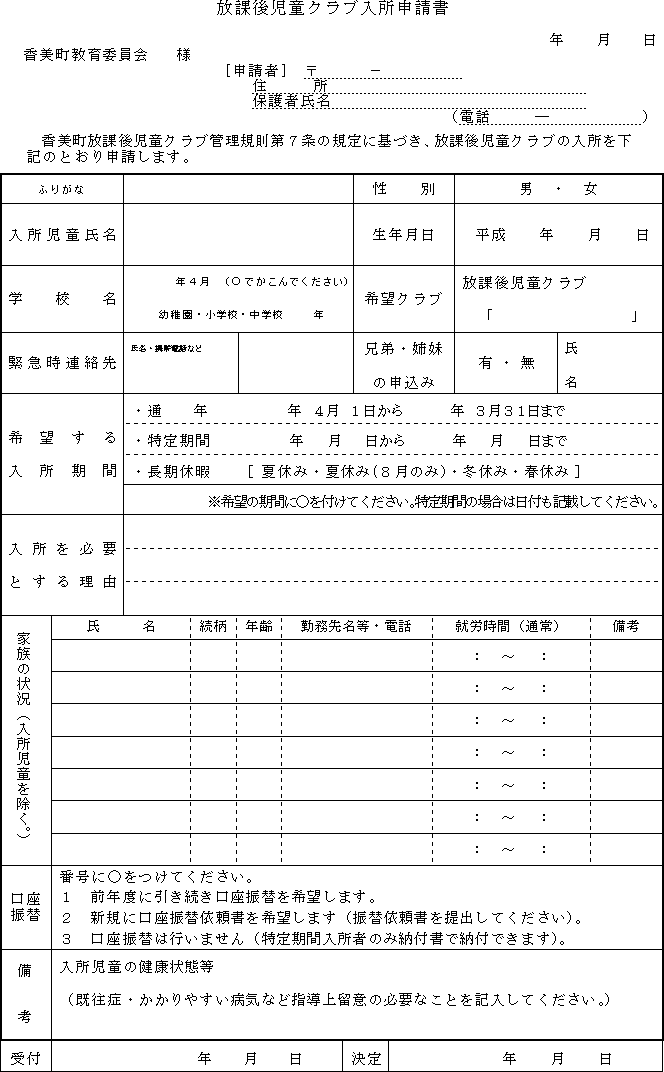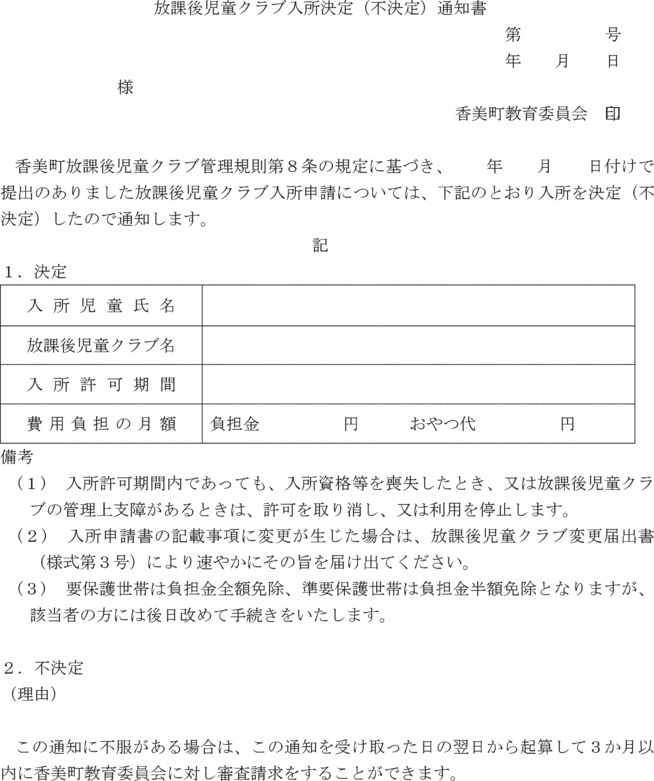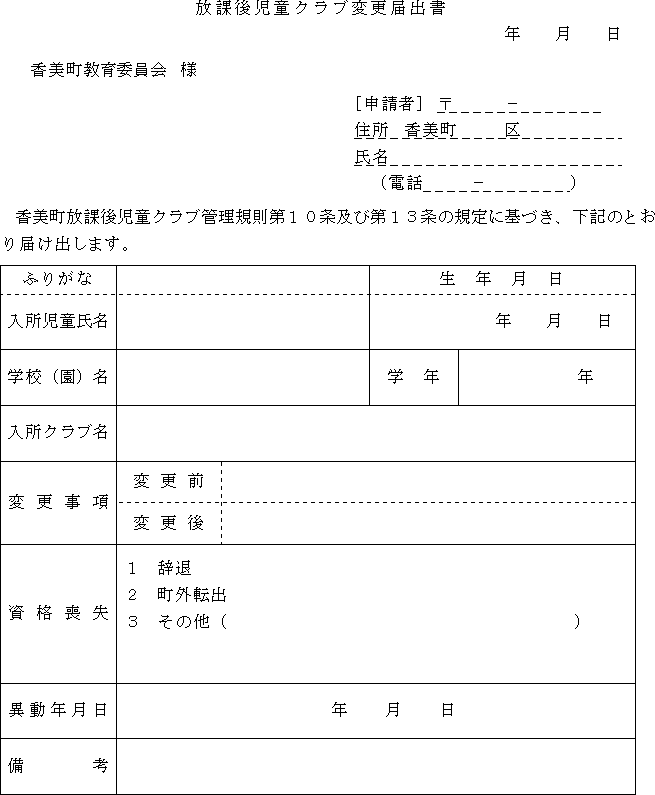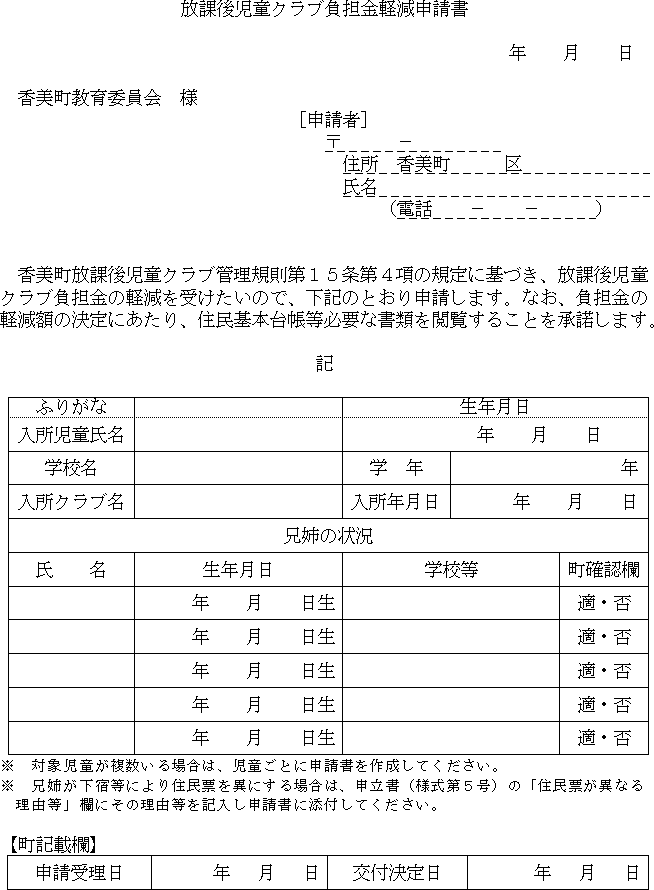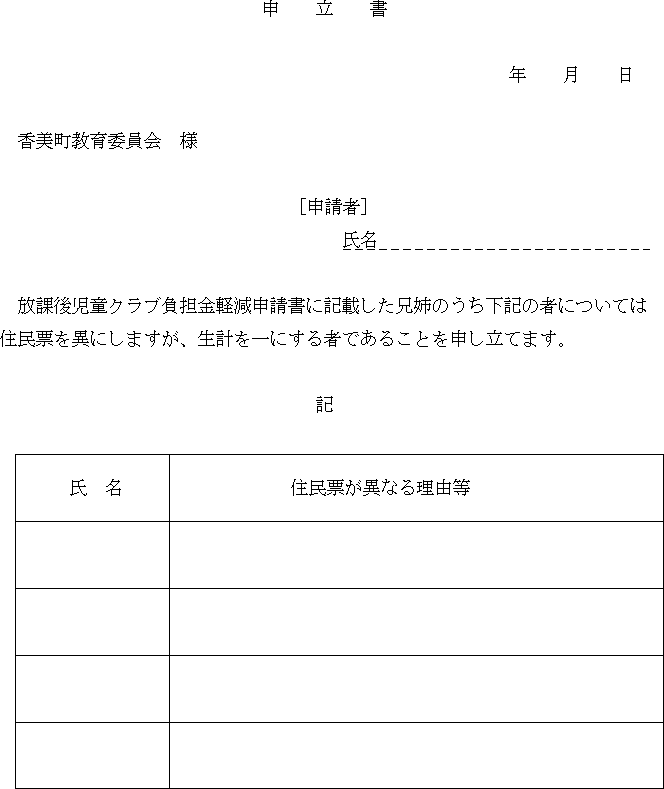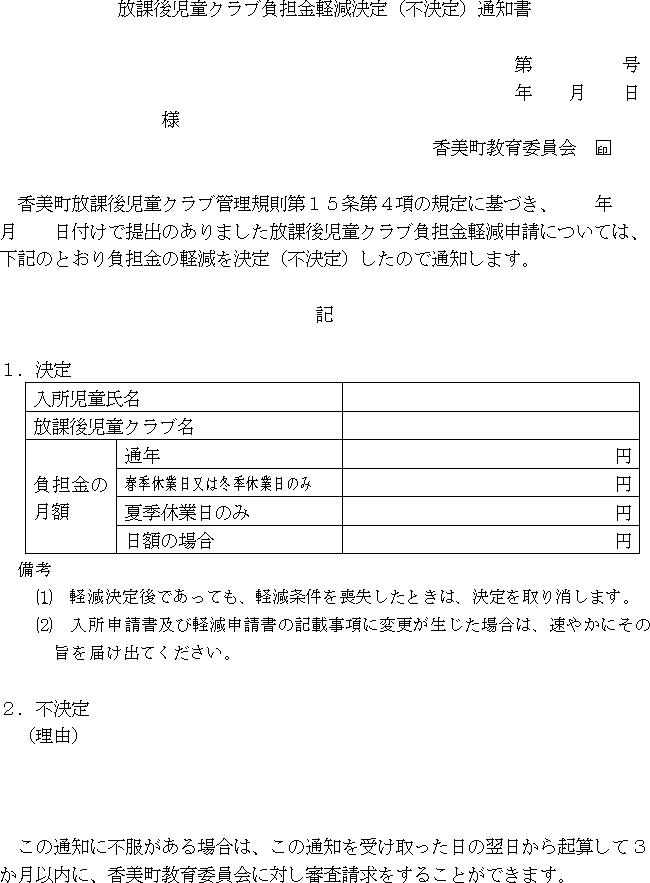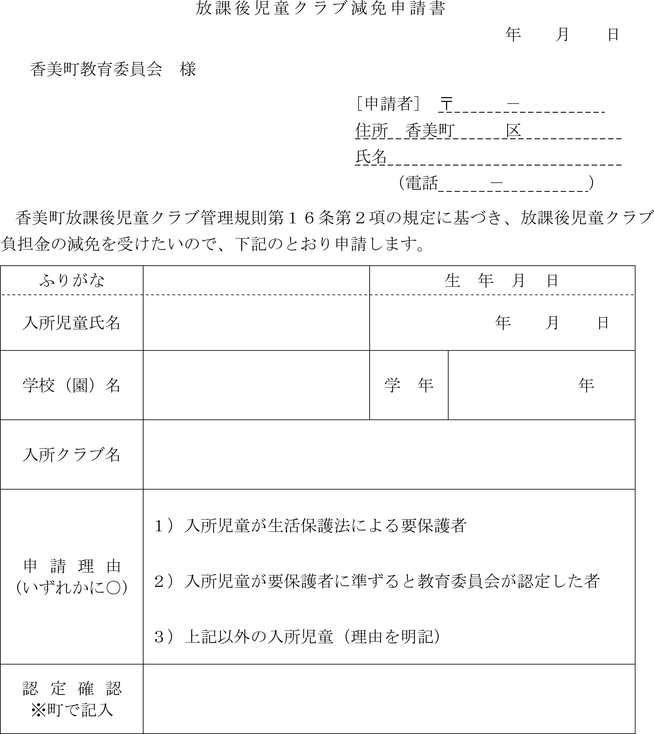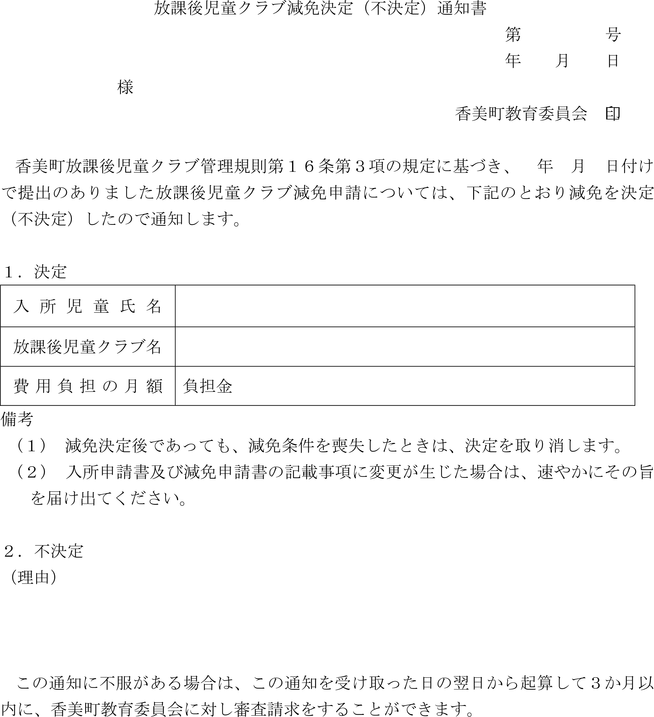○香美町放課後児童クラブ管理規則
平成25年6月27日教育委員会規則第4号
香美町放課後児童クラブ管理規則
(趣旨)
(対象児童)
第2条 放課後児童クラブに入所できる児童は、町内の幼稚園、小学校又は中学校に在籍し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者等が労働等により昼間家庭にいない幼稚園又は小学校に在籍する児童
(2) 保護者が昼間家庭にいる児童であるが、保護者が疾病等の理由により、家庭内での健全育成が困難な幼稚園又は小学校に在籍する児童
(3) 障害のある幼稚園、小学校又は中学校に在籍する児童で、前2号に掲げる家庭環境にあり、香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に健全育成上指導を必要と認めた幼稚園又は小学校に在籍する児童
(放課後児童支援員等)
2 支援員等は、次の業務を行う。
(1) 入所している児童(以下「入所児童」という。)の生活管理及び安全の保持
(2) 入所児童の社会適応性の助長
(3) 家庭及び幼稚園、小学校又は中学校との連絡
(4) 放課後児童クラブの環境整備
(定員)
第4条 放課後児童クラブの定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
放課後児童クラブスマイルかすみ | おおむね50人 |
放課後児童クラブスマイルおくさづ | おおむね10人 |
放課後児童クラブスマイルさづ | おおむね10人 |
放課後児童クラブスマイルしばやま | おおむね10人 |
放課後児童クラブスマイルながい | おおむね15人 |
放課後児童クラブスマイルあまるべ | おおむね10人 |
放課後児童クラブふれあいむらおか | おおむね30人 |
放課後児童クラブふれあいうづか | おおむね30人 |
放課後児童クラブふれあいいそう | おおむね30人 |
放課後児童クラブふれあいおじろ | おおむね10人 |
(開所日)
第5条 放課後児童クラブの開所日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日は、休所日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)
(3) 8月13日から15日までの日(第1号に掲げる休日を除く。)
(4) 教育委員会が特に必要と認めた日
(開所時間)
第6条 放課後児童クラブの開所時間は、次の各号に掲げる時間とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日(次号に掲げる日を除く。)幼稚園、 小学校又は中学校の終業の時刻から午後6時まで
(2) 土曜日並びに幼稚園、小学校又は中学校の休業日、春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日 午前7時30分から午後6時まで
(入所の申請)
第7条 放課後児童クラブに入所を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ入所申請書(
様式第1号。以下「入所申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(入所の許可)
第8条 教育委員会は、前条の規定に基づく入所申請の許可又は不許可について、放課後児童クラブ入所決定(不決定)通知書(
様式第2号)により、当該保護者に通知するものとする。
(入所の優先順位)
第9条 児童の入所については、家庭状況等により緊急性の高い年齢が小さい者から優先順位を決定する。
(変更の届出)
第10条 入所児童の保護者は、第7条の入所申請書の記載事項に変更があったときは、放課後児童クラブ変更届出書(
様式第3号。以下「変更届出書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(入所の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を拒否し、又は入所児童を帰宅させることができる。
(1) 疾病があり、他に感染するおそれのある場合
(2) その他教育委員会が不適当と認める場合
(許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の許可を取り消し、又は放課後児童クラブの利用を一時停止させることができる。
(1) 児童が第2条に定める入所の資格を失った場合
(2) 教育委員会が放課後児童クラブの管理運営上支障があると認める場合
(3) 第14条に規定する負担金等を3か月以上滞納した場合
(退所の届出)
第13条 保護者は、入所児童を放課後児童クラブから退所させようとするときは、変更届出書により、教育委員会に退所の届出をしなければならない。
(保護者負担金等)
第14条 保護者は、放課後児童クラブを利用したとき、当該月分の負担金等を翌月の20日までに納入しなければならない。
2 負担金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 幼稚園に在籍する児童 児童一人につき、
別表1により算定した額とする。
ア 第4階層の世帯であって、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)第1学年から第3学年までに在学する児童、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する児童、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける児童、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける児童が同一世帯に2人以上いる場合は、次表の第1欄に掲げる児童の負担金は、第2欄により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
(ア) アに掲げる施設を利用している児童のうち、年長者から数えて第2子となる就学前児童 | 負担金 ×0.5 |
(イ) アに掲げる施設を利用している児童のうち、年長者から数えて第3子以降となる就学前児童 | 0円 |
イ 第3階層の世帯であって、利用児童の保護者に監護される者その他これに準ずる者として子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の2で定める者で、利用児童の保護者と生計を一にするもの(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合は、次表の第1欄に掲げる児童の負担金は、第2欄により計算して得た額とする。ただし、児童の属する世帯が母子世帯等の場合の(ア)の第2欄については、0円とする。
第1欄 | 第2欄 |
(ア) 特定被監護者等のうち、年長者から数えて第2子となる就学前児童 | 負担金 ×0.5 |
(イ) 特定被監護者等のうち、年長者から数えて第3子以降となる就学前児童 | 0円 |
ウ 第2階層の世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合は、特定被監護者等のうち、年長者から数えて第2子以降となる就学前児童の負担金は0円とする。
(2) 小学校又は中学校に在籍する児童 児童1人につき、
別表2に定めるとおりとする。
3 保険料及びおやつ代の額は、実費とする。ただし、幼稚園に在籍する児童の保険料は、無料とする。
4 前2項の規定にかかわらず、当該月の利用日数(春季休業日、夏季休業日又は冬季休業日期間を除く。)が7日に満たない場合又は教育委員会が必要と認めた場合においては、第2項に規定する負担金の額を幼稚園に在籍する児童は
別表3に定める額とし、小学校又は中学校に在籍する児童は日額1,000円とし、前項に規定するおやつ代を1日50円とする。
5 教育委員会が必要があると認めたときに徴収する協力費の額は、別に定める額とする。
6 既納の負担金等は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、その負担金等の全部又は一部を還付することができる。
(負担金の軽減)
第15条 教育委員会は、前条第2項第2号に規定する児童のうち、第3子(満18歳未満(ただし、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間を含む。)であって、入所児童の保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者を除く。))のうち、年長の子どもから順に3人目の者をいう。)以降の者に係る負担金を減額することができる。
2 前項の減額できる額は、前条第2項第2号及び第4項により算出した負担金の額から、当該負担金の額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 当該児童が放課後児童クラブを利用した月の属する年度(放課後児童クラブを利用した月が4月から8月までの間にあっては、その前年度)について課された保護者の市町村民税所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の規定による所得割をいう。ただし、同法第328条の規定による退職所得等に係る所得割を除く。)を合算した額が
別表4の区分ごとに定める額以上となる場合は、前2項の規定による軽減は行わないものとする。
4 負担金の軽減を希望する入所児童の保護者は、放課後児童クラブ負担金軽減申請書(
様式第4号。以下「軽減申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、入所児童の保護者と生計を一にする兄姉で当該児童と住民票を異にする者がある場合は、申立書(
様式第5号)を軽減申請書に添付しなければならない。
5 教育委員会は、前項の規定に基づく軽減申請の決定又は不決定について、放課後児童クラブ負担金軽減決定(不決定)通知書(
様式第6号)により、当該保護者に通知するものとする。
(負担金の減免)
第16条 教育委員会は、次の各号に掲げる理由があると認めるときは、第14条第2項及び第4項の規定により算出し、又は前条第1項及び第2項の規定により軽減した負担金を当該各号に掲げる額について減免することができる。
(1) 入所児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者 全額
(2) 入所児童が生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定した者 半額
(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認めた入所児童 全額又は一部
2 負担金の減免を希望する入所児童の保護者は、放課後児童クラブ減免申請書(
様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定に基づく減免申請の決定又は不決定について、放課後児童クラブ減免決定(不決定)通知書(
様式第8号)により、当該保護者に通知するものとする。
(送迎)
第17条 入所児童の送迎は、保護者の責任において行うものとする。
(運営委員会)
第18条 放課後児童クラブを円滑に運営するため、香美町放課後児童クラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、保護者、支援員等及び識見を有する者等で組織する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、放課後児童クラブの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に香美町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成24年香美町教育委員会告示第12号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成27年3月19日教委規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年3月23日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第14条関係)
幼稚園に在籍する児童の負担金の額
階層区分 | 定義 | 通年利用者 | 春季休業日又は冬季休業日のみの利用者 | 夏季休業日のみの利用者 |
(月額) | (月額) | (月額) |
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税の所得割の額のない世帯 | 3,500円 | 1,750円 | 3,500円 |
| 母子世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 |
3 | 市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 77,101円未満 | 7,000円 | 3,500円 | 7,000円 |
| 母子世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 |
4 | 77,101円以上 | 7,000円 | 3,500円 | 7,000円 |
別表2(第14条関係)
小学校又は中学校に在籍する児童の負担金の額 |
通年利用者 | 春季休業日又は冬季休業日のみの利用者 | 夏季休業日のみの利用者 |
(月額) | (月額) | (月額) |
7,000円 | 3,500円 | 7,000円 |
別表3(第14条関係)
当該月の利用日数が7日に満たない場合又は教育委員会が必要と認めた場合の幼稚園に在籍する児童の負担金の額
階層区分 | 日額 |
第1階層 | 0円 |
第2階層 | 500円 |
| 母子世帯等 | 0円 |
第3階層 | 1,000円 |
| 母子世帯等 | 0円 |
第4階層 | 1,000円 |
別表4(第15条関係)
小学校又は中学校に在籍する児童の負担金軽減の所得制限額
区分 | 保護者の市町村民税所得割額を合算した額 |
ア イに該当する児童以外の児童 | 155,500円 |
イ 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第22条に掲げる第3子以降の児童 | 169,000円 |
備考 市町村民税所得割の算出方法は子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号並びに内閣府令第21条及び第21条の2に基づくものとする。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第10条、第13条関係)
様式第4号(第15条関係)
様式第5号(第15条関係)
様式第6号(第15条関係)
様式第7号(第16条関係)
様式第8号(第16条関係)